大切な親族が亡くなったとき、私たちは深い悲しみの中にいながらも、現実的な手続きに向き合わなければなりません。
葬儀の準備から始まり、役所への届け出、相続に関する手続き、さらには故人が利用していたサービスや契約の整理など、多くの作業が短期間のうちに必要となります。
しかし、慣れないうえに期限が決まっているものも多く、「何から手をつけたらいいのかわからない」と戸惑う方も少なくありません。
また、手続きの遅れや漏れは、後のトラブルや余計な負担につながることもあります。
この記事では、親族が亡くなった際に必要となる手続きを時系列でわかりやすくまとめました。
一つ一つの手続きを把握し、冷静に対応できるように、具体的な流れと注意点を丁寧に解説していきます。
いざという時に、少しでも心の負担を減らし、大切な人をきちんと送り出すための助けとなれば幸いです。
第1章:すぐに行うべき手続き(死亡直後〜3日以内)
親族が亡くなった直後は、感情の整理がつかない中でも、迅速に進めなければならない手続きがいくつかあります。この章では、特に死亡後すぐに行うべき重要な手続きについて解説します。
死亡診断書・死体検案書の受け取り
まず、死亡診断書(自然死の場合)または死体検案書(事故死・異状死の場合)を医師から受け取る必要があります。
これがないと死亡届を提出できず、葬儀や火葬も進められません。
- 自然死の場合:かかりつけ医や病院の医師が発行
- 異状死(事故死・突然死など)の場合:警察を通じて検死が行われ、死体検案書が発行される
⚡ ポイント
死亡診断書と死体検案書は、後の手続きで何度もコピーが必要になるので、事前に複数枚コピーをとっておきましょう(役所によってはコピーを認めない場合もあるため、原本の追加発行が可能か確認を)。
親族や関係者への連絡
次に、親族、近しい友人、勤務先などへ訃報を伝えます。
葬儀の日程調整にも関わるため、早めの連絡が必要です。
- 電話、メール、LINEなどを使って連絡
- 連絡リスト(続柄、名前、電話番号など)をあらかじめ作成しておくとスムーズ
⚡ ポイント
連絡内容は「いつ、どこで亡くなったか」「今後の予定(通夜・葬儀)」「服装(平服か喪服か)」などを簡潔にまとめて伝えます。
葬儀社・火葬場の手配
死亡が確認されたら、すぐに葬儀社に連絡し、葬儀の打ち合わせを行います。
また、火葬場の予約も早めに行う必要があります。
- 葬儀社を事前に決めていない場合は、複数社を比較するのが理想ですが、時間がない場合は地域の評判や、病院提携の葬儀社に依頼するケースもあります
- 火葬場の空き状況によって葬儀日程が決まるため、予約は最優先
⚡ ポイント
葬儀社が手続き代行をしてくれるプランもあるので、負担を軽減したい場合はプラン内容を確認しましょう。
死亡届の提出(7日以内)
法律上、死亡後7日以内に死亡届を役所に提出する義務があります。
通常、葬儀社が代行してくれることも多いですが、自分で提出する場合は以下を準備します。
- 死亡診断書(または死体検案書)と一体になった死亡届用紙
- 提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場
⚡ ポイント
届出人は通常、親族・同居者・家主・管理人など。押印は原則不要ですが、自治体によって求められることもあるため、印鑑を持参すると安心です。
火葬許可証の取得
死亡届を提出すると、役所から火葬許可証が発行されます。
この書類がないと火葬できないため、必ず受け取ってください。
- 火葬許可証は、火葬終了後に「埋葬許可証」として返却され、納骨時に使用します
⚡ ポイント
火葬許可証は、火葬場に提出するため、葬儀社が保管・持参してくれるケースもありますが、失くさないように注意しましょう。
第2章:葬儀・火葬・納骨に関する手続き
死亡後の初期手続きが終わったら、次に待っているのが葬儀、火葬、納骨です。
これらは宗教や地域によって多少流れが異なりますが、基本的な進め方と注意点について解説していきます。
葬儀の流れと注意点
葬儀の流れは、大きく分けて以下のようになります。
- 通夜
- 亡くなった日の翌日または翌々日に行われることが多い
- 近親者や親しい友人を中心に、故人を偲びます
- 葬儀・告別式
- 宗教儀式を行う「葬儀」と、故人との最後のお別れの場である「告別式」がセットで行われることが多い
- 通夜翌日に行われることが一般的
- 出棺・火葬
- 告別式後、火葬場に向かい、火葬を行います
- 収骨(拾骨)
- 火葬後、骨壺に遺骨を納めます
⚡ ポイント
- 葬儀の規模(家族葬・一般葬・社葬など)や形式(仏式・神式・キリスト教式・無宗教)を事前に決めておきましょう。
- 喪主を誰にするか、挨拶や弔辞を誰に頼むかも、早めに相談することが重要です。
役所への火葬終了届
火葬が終了したら、火葬場から渡される証明書を持って、役所に火葬終了届を提出します。
これにより、役所側で死亡者の住民登録が抹消される手続きが進みます。
- 通常、葬儀社が代行してくれる場合もあります
- 住民票や戸籍謄本の変更にも関連するため、確実に提出しましょう
⚡ ポイント
火葬終了届の提出が遅れると、後の行政手続き(年金、保険、相続など)に影響する可能性があるので注意してください。
納骨・埋葬許可証の取得と手続き
火葬終了後に火葬場から返却される「火葬許可証」は、埋葬許可証として使用します。
この許可証を持って、墓地や納骨堂に納骨する手続きを行います。
- 納骨する際には、墓地管理者や寺院に事前連絡し、日程を調整します
- 埋葬許可証は、納骨時に提出が必要(原則として原本)
⚡ ポイント
- 墓地が決まっていない場合は、永代供養墓や納骨堂などの選択肢も検討しましょう。
- 菩提寺がある場合は、戒名料や納骨式の読経料が必要なこともあるため、費用面も事前に確認しておくと安心です。
第3章:死亡後14日以内に行う手続き(役所関係)
葬儀や火葬が終わると、少し落ち着きますが、死亡後14日以内に行わなければならない役所への届け出や手続きがいくつかあります。
この章では、それらの具体的な手続きと注意点について詳しく解説します。
健康保険の資格喪失手続き
故人が健康保険に加入していた場合、その資格を喪失したことを届け出る必要があります。
- 国民健康保険:市区町村役場で「国民健康保険資格喪失届」を提出
- 職場の健康保険(社会保険):勤務先が手続きを行う。勤務先に連絡して確認
- 後期高齢者医療制度(75歳以上):市区町村役場で喪失手続き
⚡ ポイント
健康保険証を返却する必要があるので、必ず持参しましょう。
また、すでに支払った保険料の一部が還付される場合もあるので、確認を忘れずに。
介護保険の資格喪失手続き
故人が要介護認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失届も必要です。
- 市区町村役場の介護保険担当窓口に「介護保険被保険者証」を返却し、資格喪失の届け出を行います
⚡ ポイント
介護保険に関するサービス利用中だった場合、未清算分の費用が発生していることもあるので、施設や事業所にも連絡しておきましょう。
国民年金・厚生年金の停止申請
故人が年金受給者であった場合、死亡によって年金の支給は停止されます。これも14日以内に手続きが必要です。
- 国民年金のみ加入者:市区町村役場で「死亡届」と「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出
- 厚生年金受給者:年金事務所または街角の年金相談センターに届け出
提出に必要な書類例:
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届のコピー
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
⚡ ポイント
年金の停止手続きを怠ると、年金が誤って振り込まれ、後日返還手続きが必要になる場合があります。
また、場合によっては「未支給年金」の請求ができることもあるので、併せて確認しましょう。
第4章:相続に関する手続き
親族が亡くなった後には、相続という大きな手続きが待っています。
相続は法律に基づいて進める必要があり、間違いや漏れがあると後々トラブルになりかねません。
この章では、相続に関して必要なステップを順番に解説していきます。
遺言書の有無確認と検認
まず最初に確認すべきは、遺言書の有無です。
- 遺言書がある場合は、家庭裁判所に提出し、検認という手続きを受ける必要があります
- 検認とは、「この遺言書が確かに存在していた」という事実を家庭裁判所が記録する手続きで、内容の有効性を判断するものではありません
⚡ ポイント
遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません!
開封前に必ず家庭裁判所に届け出て、正式に開封する流れが必要です(封印されていない遺言書も同様です)。
相続人の確定
次に、相続人を確定させます。
- 配偶者は必ず相続人
- その他は、子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹の順番で相続人が決まる
- 誰が相続人になるかを確定するため、戸籍謄本を取り寄せる必要あり
⚡ ポイント
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍含む)を収集する必要があります
- 戸籍の取り寄せには時間がかかることもあるので、早めに動きましょう
遺産分割協議
遺言書がない場合や、遺言書に書かれていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。
- 財産の内容を調査・リストアップ(預貯金、不動産、株式、車、負債など)
- 相続人全員が集まって、誰が何を相続するかを話し合う
- 話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、全員の署名・押印を行う
⚡ ポイント
一人でも協議に反対する相続人がいると、家庭裁判所の調停や審判に持ち込む必要が出てきます。
なるべく冷静に、円満な話し合いを心がけましょう。
相続税申告(10か月以内)
遺産総額が基礎控除額(「3000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。
- 申告期限は、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」
- 相続税の申告は税務署に対して行う
- 不安な場合は税理士に相談するのがおすすめ
⚡ ポイント
申告と納税の両方が10か月以内です。延滞すると加算税・延滞税がかかるので、要注意です。
不動産の名義変更など
故人名義の不動産がある場合、**名義変更(相続登記)**を行う必要があります。
- 相続登記は、2024年4月1日から義務化されました
- 登記申請先は、不動産所在地の管轄法務局
- 必要書類例:遺産分割協議書、戸籍謄本、不動産の固定資産税評価証明書など
相続登記の期限について
期限は、
「相続が発生したことを知った日から3年以内」
と定められています。
期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
⚡ ポイント
- 相続発生から3年以内に登記を完了すること
- 遺産分割協議中などで登記が間に合わない場合は、以下の方法で対応できます
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、
「とりあえず自分が相続人であることだけを法務局に申請する登記」のことです。
- 相続登記の代わりに「私はこの不動産の相続人です」とだけ申告する
- 本格的な遺産分割や登記変更がまだできていない段階でも、義務違反を回避できる
- 相続登記の3年以内の義務に対する「応急処置」として使える
【相続人申告登記に必要な書類例】
- 被相続人(故人)の死亡が記載された戸籍謄本
- 相続人自身の戸籍謄本や住民票
- 不動産の登記事項証明書または固定資産評価証明書
⚡ ポイント
- 相続人申告登記をしておけば、相続登記の義務違反にはなりませんが、正式な名義変更ではないため、売却や担保設定はできません。
- 後日、改めて正式な相続登記(名義変更)が必要になります。
- 司法書士に依頼するとスムーズに進められます。
第5章:その他必要な手続き
親族の死後には、役所や相続以外にも、生活に関わるさまざまな契約や手続きを整理する必要があります。
この章では、忘れがちなその他の重要な手続きについて解説します。
銀行口座の凍結解除と手続き
故人が持っていた銀行口座は、死亡の事実が判明した時点で凍結され、出金や振込ができなくなります。
相続人は、口座凍結を解除して預金を引き出すための手続きを行う必要があります。
手続きの基本の流れ
- 各銀行に連絡し、必要書類を確認
- 必要書類を準備して提出
- 預金の相続手続きを進める
必要書類の例
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本や住民票
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人の本人確認書類
⚡ ポイント
銀行によって手続き方法や書類が若干異なるので、事前に必ず確認しましょう。
また、故人の口座から葬儀費用の支払いを希望する場合、銀行によっては一部払い戻しができるサービスもあります。
クレジットカード・公共料金・サブスクリプションの解約
故人が契約していた各種サービスも、速やかに解約手続きを行う必要があります。
主な解約対象
- クレジットカード(JCB、VISA、MasterCardなど)
- 電気・ガス・水道
- 携帯電話、インターネット
- サブスクリプション(Netflix、Amazon Prime、Spotifyなど)
- 新聞、雑誌の定期購読
解約の流れ
- 連絡先(カスタマーセンターなど)に死亡の旨を連絡
- 死亡証明書(コピー可)が必要な場合もあるので準備
- 残高清算や機器返却が求められる場合は速やかに対応
⚡ ポイント
支払いが自動引き落としになっている場合、放置すると延々と課金が続く危険があります。
必ず一つ一つチェックリストを作成して、漏れなく解約しましょう。
生命保険金の請求手続き
故人が加入していた生命保険がある場合は、保険金の請求手続きを行う必要があります。
通常、死亡後すぐに請求でき、これを怠ると支払期限が過ぎてしまうこともあるので、早めの対応が重要です。
手続きの基本の流れ
- 保険会社に連絡し、死亡の報告をする
- 必要書類を取り寄せる
- 書類を記入・準備し、提出する
- 審査・確認後、保険金が支払われる
主な必要書類
- 死亡診断書(または死体検案書)のコピー
- 保険証券
- 請求書(保険会社所定のもの)
- 受取人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 受取人の口座情報
⚡ ポイント
- 生命保険の請求期限は通常3年以内ですが、保険会社によって異なる場合もありますので、必ず確認しましょう。
- 受取人が指定されている場合、相続手続きとは別に、受取人個人が直接保険金を受け取る形になります(原則、生命保険金は相続財産には含まれません)。
SNSアカウントやスマホ契約の処理
デジタル社会の現代では、故人のSNSアカウントやスマホ契約も忘れてはなりません。
SNSアカウントの対応例
- Facebook:「追悼アカウント」設定やアカウント削除申請が可能
- Instagram:追悼アカウント化または削除申請
- Twitter(X):遺族による削除申請
- LINE:利用停止・アカウント削除
スマホ契約の処理
- 携帯会社(docomo、au、SoftBankなど)に死亡届を提出し、契約解除
- スマホ端末の返却が求められる場合もあり
⚡ ポイント
SNSやスマホ契約情報は、本人のパスワードが必要な場合も多いため、事前に「エンディングノート」などで管理しておくと安心です。
死後に個人情報が悪用されないよう、しっかり手続きをしておきましょう。
まとめ
親族が亡くなると、悲しみの中で冷静に進めなければならない手続きが数多くあります。
本記事では、死亡直後から数か月以内に行う必要がある重要な手続きをまとめてご紹介しました。
特に重要なポイントは以下の通りです。
- 死亡直後に必要な死亡診断書の取得と、葬儀・火葬の手配
- 14日以内に行う健康保険や年金関連の届け出
- 相続手続きでは、遺言書の確認と相続人の確定、遺産分割協議の実施
- 不動産の相続登記は2024年から義務化され、相続を知った日から3年以内に行う必要がある
- 相続がまとまらない場合でも、相続人申告登記で義務違反を回避できる
- 銀行口座、クレジットカード、サブスクリプション、SNSアカウントなど、生活に密着した契約の整理も忘れずに
手続きは一つ一つが煩雑ですが、リスト化して順番に進めることで負担を減らせます。
また、必要に応じて、専門家(行政書士・司法書士・弁護士・税理士)に相談することも視野に入れましょう。
最後に、大切な人を見送った後は、ご自身の体調にも十分に気を配ってくださいね。
無理をせず、周囲の助けを借りながら、一歩ずつ進めていきましょう。

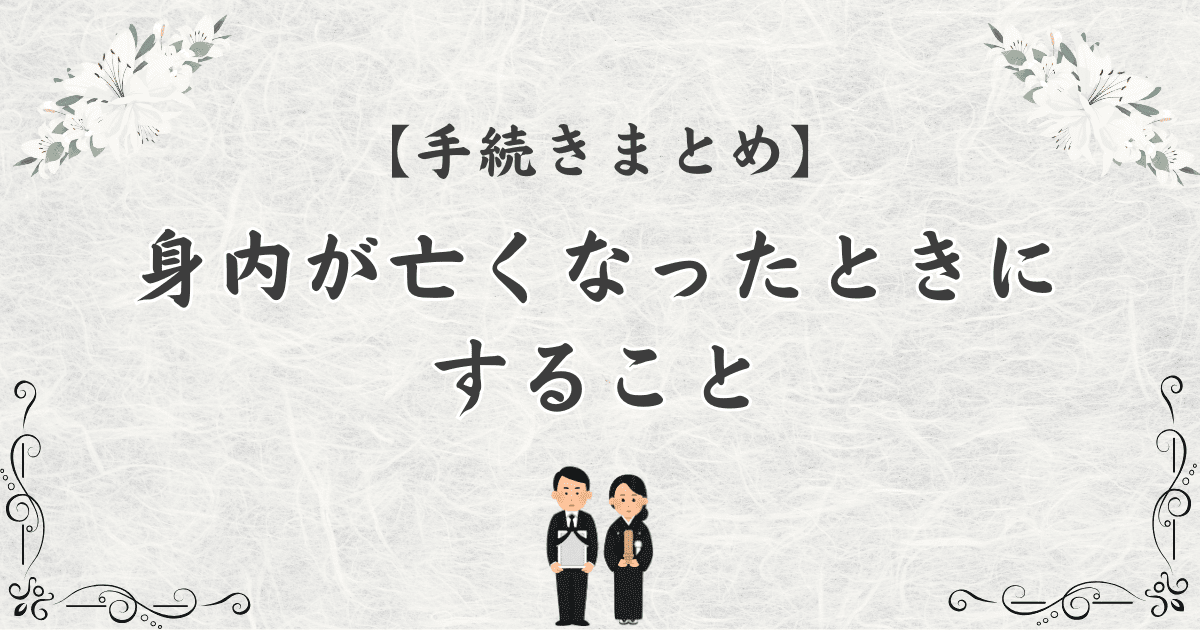


コメント