臨床心理学は、心の問題を科学的に理解し、人の「こころ」を支えるための心理学です。今回は、臨床心理学のはじまりから現在に至るまでの歴史を、海外の動きと日本の発展の両面からわかりやすく解説します。
臨床心理学の誕生とウィトマーの心理クリニック
臨床心理学の出発点とされるのが、ライトナー・ウィトマー(Lightner Witmer)の活動です。
1896年、彼はアメリカ・ペンシルベニア大学に世界初の心理クリニックを開設しました。ウィトマーは、知的障害や学習困難のある子どもたちの支援を目的に、心理学の知見を応用する試みを行いました。
この「心理クリニック」は、医療モデルに基づく現在の臨床心理学の原型であり、臨床心理学という言葉そのものもウィトマーが提唱したといわれています。
フロイトと精神分析の登場
同時期にヨーロッパで誕生したのが、ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)による精神分析(psychoanalysis)です。
フロイトは、無意識の重要性に注目し、ブロイアー(Josef Breuer)とともに『ヒステリー研究』を出版。無意識に抑圧された感情が身体症状となることを明らかにしました。
フロイトの理論は「力動的心理学(第一勢力)」として臨床心理学の基盤となり、多くの弟子や後継者によって広がっていきました。
ユングと分析心理学、アドラーと個人心理学
フロイトの弟子の中でも有名なのが、カール・グスタフ・ユング(Carl G. Jung)とアルフレッド・アドラー(Alfred Adler)です。
- ユングは「個人的無意識」だけでなく「集合的無意識」を提唱し、分析心理学(Analytical Psychology)を創始。
- アドラーは「劣等感」や「共同体感覚」に注目し、個人心理学(Individual Psychology)を展開しました。
これらの理論は現在の臨床心理学にも大きな影響を与えています。
第二次世界大戦と臨床心理学の拡大
第二次世界大戦中、アメリカ軍は大量の兵士の選抜や精神的サポートのために陸軍心理検査(Army Alpha/Beta test)を導入し、多数の心理学者が実務に従事しました。
この流れは戦後の心理学教育にも影響し、臨床心理士の制度や大学院での臨床教育が進む契機となりました。
行動主義から人間性心理学へ(第一勢力〜第三勢力)
臨床心理学は、以下の3つの「勢力」によって発展してきました。
- 第一勢力:力動的心理学(精神分析・ユング・アドラーなど)
- 第二勢力:行動主義心理学(ワトソン、スキナーなど、観察可能な行動に注目)
- 第三勢力:人間性心理学(マズロー、ロジャーズなど、人間の成長や可能性を重視)
中でも、マズロー(Abraham Maslow)の「自己実現理論」やロジャーズ(Carl Rogers)の「クライエント中心療法」は、人間性回復運動(Human Potential Movement)につながり、今日のカウンセリングの理論的基盤となっています。
日本における臨床心理学の発展
初期の研究者たち
日本での臨床心理学の基礎を築いたのは、以下の研究者たちです。
- 佐々木政直:精神医学と心理学の橋渡しを行い、「ステーリング氏の心理学に関する精神病理学」を紹介。
- 古澤平作:欧米の心理学を紹介し、心理学の科学的体系化を目指す。
- 森田正馬:神経症に対して「森田療法」を開発。
- 成瀬悟策:行動療法の導入と日本的応用を進める。
- 河合隼雄:ユング派心理学を日本に導入し、文化に根ざした心理臨床を展開。京都大学教育学部付属心理教育相談室の設立に関わる。
日本臨床心理学会とスクールカウンセラー
1963年には日本臨床心理学会が設立され、臨床心理学の学問的地位が確立されていきます。
1995年以降は、全国の学校にスクールカウンセラーが配置され、教育現場においても臨床心理士のニーズが拡大しました。
まとめ
臨床心理学は、ウィトマーの心理クリニックから始まり、フロイトによる精神分析、戦争と行動主義、人間性心理学の登場、そして日本での発展を経て、今では多様な理論と技法を含む総合的な学問となりました。
臨床心理士や公認心理師を目指すうえで、これらの歴史を押さえておくことはとても重要です。

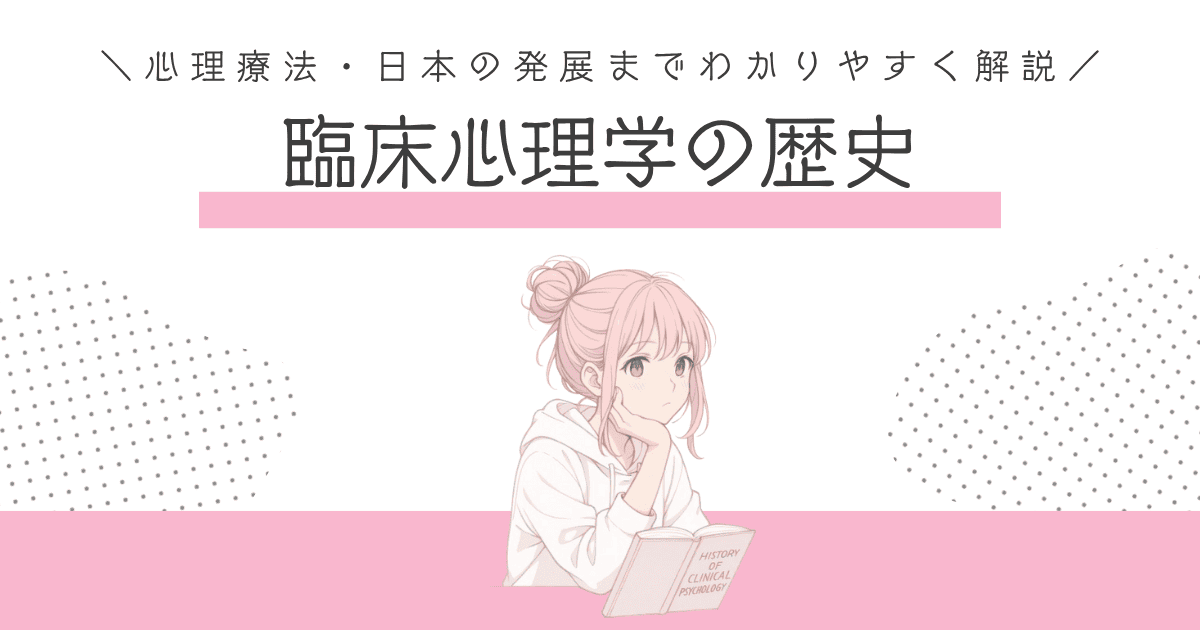

コメント